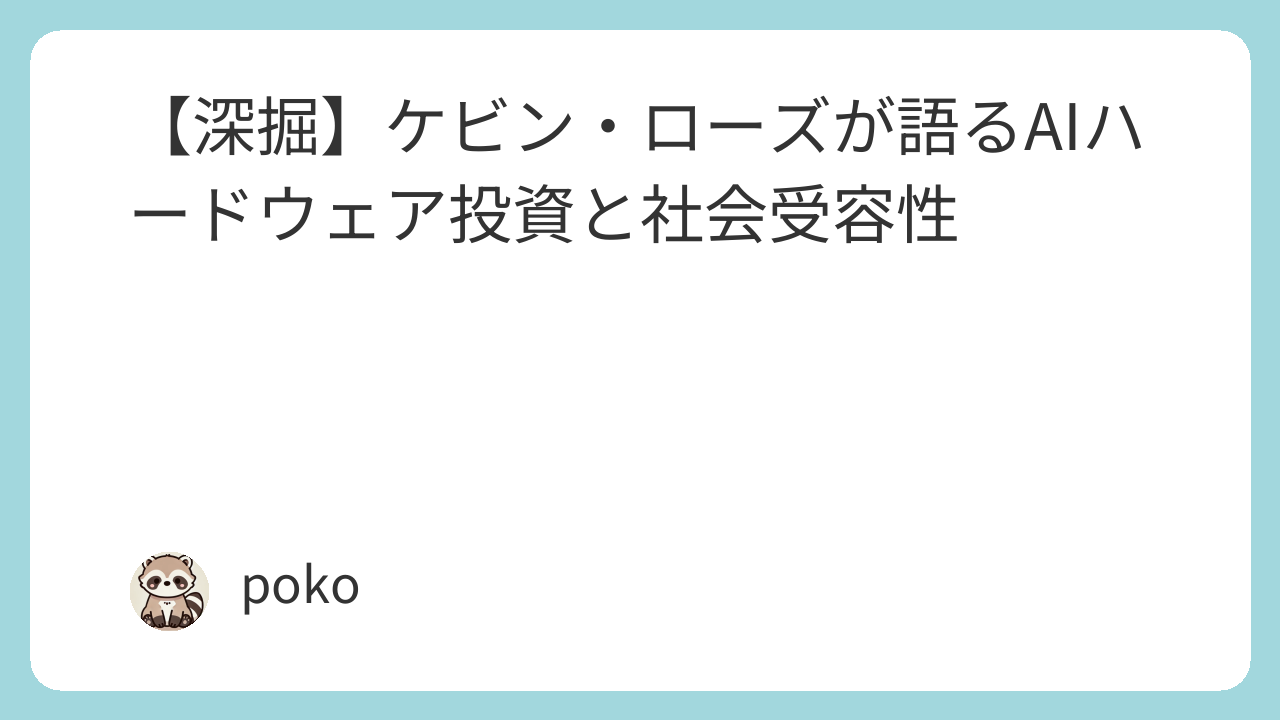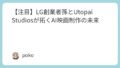著名投資家ケビン・ローズ氏は、AIハードウェア投資において「着用者に不快感を覚える製品には投資すべきではない」という直感的な評価基準を持つ。常に稼働し、会話を傍受するウェアラブルAIは、プライバシーや社会的な受容性の面で課題に直面していると指摘する。しかし同時に、AIは起業の敷居を下げ、ベンチャー投資のあり方自体を変革する可能性も秘めていると見ており、投資家には技術力だけでなく、創業者を支援する人間力が求められると説く。
ケビン・ローズが説くAIハードウェアの評価基準
ベテラン投資家のケビン・ローズ氏は、AIハードウェアへの投資判断において独自の見解を示している。彼は「もしその製品を身につけている人を見て、思わず顔を殴りたくなるようなら、おそらく投資すべきではない」と語る。
この「直感的なルール」は、彼がこれまで多くのAIハードウェアスタートアップが繰り返してきた過ちを見てきた経験に基づくものだ。Peloton、Ring、Fitbitへの初期投資家でもあるTrue Venturesのジェネラルパートナーを務めるローズ氏は、現在のAIハードウェア投資熱に対し、慎重な姿勢を保っている。
スマートグラスやAIペンダントといったAIデバイスへの評価基準は、単なる技術力に留まらない。彼は「感情的な共鳴と社会的な受容性」こそが、成功するウェアラブル製品を失敗作から隔てる要素だと強調する。特に、Ouraのボードメンバーを務めた経験から、この見識を深めたという。
ウェアラブルAIが直面する社会受容性の課題
ケビン・ローズ氏は、現在のウェアラブルAIデバイスの多くが、ユーザーのプライバシーに関する社会的な規範を侵害していると懸念する。特に「常に周囲の会話を聞き取っている」ような装着型AIは、人間関係における社会受容性の大きな壁に直面すると指摘する。
彼自身も、過去に話題となったHumane AIペンダントを試用した際、妻との口論中に記録された会話データを使おうとして、その不健全さに気づいたという。「AIピンのログを見て口論に勝とうとするのは健全ではない」と述べ、自身のAIハードウェア利用を中止した経緯がある。
また、彼はAIを「何にでも後付けしようとする」風潮を批判。単に観光地で建造物の名前を教えてくれるといった限定的な利用事例では不十分だと語る。写真アプリで背景から人物を消去する機能などを例に挙げ、「AIが世界を台無しにしている」と警鐘を鳴らし、ウェアラブルAIの感情的評価の重要性を訴えている。
ローズ氏は、AIの現状を「ソーシャルメディアの黎明期」になぞらえ、現在の安易な決断が将来的に大きな後悔につながる可能性を危惧する。AIがもたらすプライバシー侵害や情報操作は、装着型AIの社会受容性テスト方法を根本から再考させる必要がある。
AIが変革する起業とベンチャー投資の未来
ケビン・ローズ氏は、AIの進化が起業とベンチャー投資のあり方を劇的に変えている点には深く楽観的な見方を示している。AIコーディングツールなどの発展により、起業家が製品を開発し市場に投入するまでの敷居が日々低くなっていると指摘した。
彼の同僚がAIツールを活用し、LAからサンフランシスコへの移動中に完璧なアプリを構築・展開できた事例を挙げ、わずか半年前と比較して開発期間が大幅に短縮されたことを強調。今後数ヶ月以内に、エラーが皆無に近い状態で開発が進められるようになると予測する。
このようなAIハードウェア技術の進化は、ベンチャーキャピタル業界にも大きな影響を与える。起業家は資金調達の時期を遅らせたり、外部資金なしで事業を進めたりすることが可能になる。これにより、VCの役割は技術的な専門知識提供から、創業者の長期的なパートナーとして「感情的な問題」を解決するEQの高い支援者へとシフトすると見ている。
投資家ケビン・ローズが求める「不可能への軽視」
ケビン・ローズ氏は、自身の投資哲学として、Google Ventures時代にラリー・ペイジから受けた助言を挙げる。「不可能なことに対する健全な軽視」こそが、投資家として見るべき重要な要素だという。
彼は、単に既存のアイデアを改善するだけでなく、誰もが「ひどいアイデアだ」「なぜそんなことをするのか」と疑問を呈するような、大胆で革新的な構想を持つ創業者を求めている。彼らは、AIハードウェアのような新しい領域で、既存の常識を打ち破る可能性を秘めている。
たとえ最初のアイデアが成功しなくても、そのような挑戦的な思考を持つ創業者であれば、二度目の投資も喜んで行うとローズ氏は語る。AIが社会に深く浸透する中で、既存の枠にとらわれず、新たな価値創造に挑む創業者こそが、未来を切り開くと信じている。
参考リンク
- The Role of AI in Hospitals and Clinics: Transforming Healthcare in … | Source: pmc.ncbi.nlm.nih.gov
- AI revolutionizing industries worldwide: A comprehensive overview … | Source: www.sciencedirect.com
- The Emergence of AI-Based Wearable Sensors for Digital Health … | Source: pmc.ncbi.nlm.nih.gov
- TechCrunch Disrupt 2026