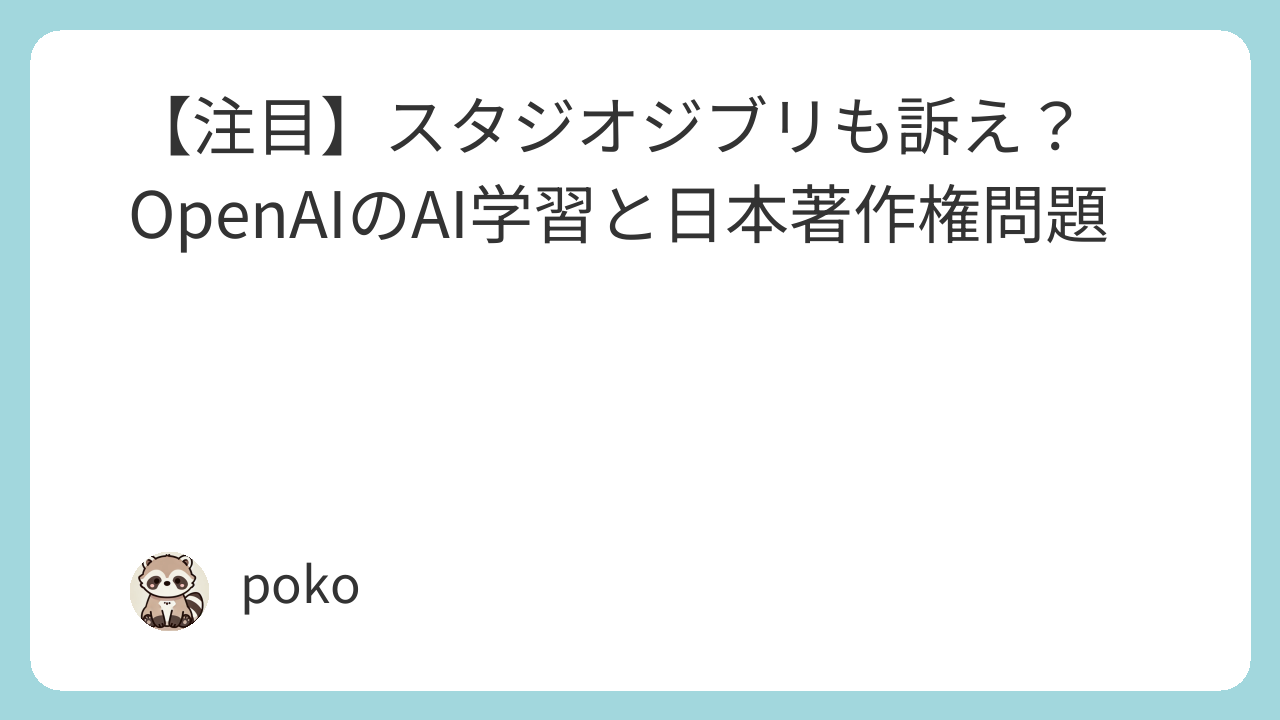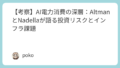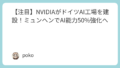OpenAIのAI学習における著作権侵害問題が深刻化している。日本のコンテンツ海外流通促進機構(CODA)は、OpenAIに対し、無断でのAI学習データ利用停止を要求した。特にスタジオジブリの作品は、生成AIによって模倣される事例が多発しており、強い懸念が表明されている。米国ではAI学習における著作権法の解釈が不明瞭だが、日本独自の法観点から法的措置の可能性も指摘されている。
CODAがOpenAIに要求:AI学習と著作権侵害
日本のコンテンツ海外流通促進機構(CODA)は直近、OpenAIに対し書簡を送付し、著作権で保護されたコンテンツのAI学習への無許可利用停止を要求したと複数のメディアが報じた。CODAはソニーのアニプレックスやバンダイナムコといった日本の大手パブリッシャーを代表する組織であり、AI開発における著作物利用問題への懸念を示している。
この要求は、特にOpenAIが提供する動画生成AI「Sora」などの生成AI製品が、許可なく著作物を利用し、コンテンツホルダーに損害を与えているとの認識に基づく。CODAは、加盟企業が所有する膨大な著作物が、AI学習データとして無断で利用されている現状に異議を唱えている。これは、AI学習と著作権のバランスを巡る国際的な議論に一石を投じる動きと言える。
CODAは、AI開発者が著作権者の許諾を得ずに著作物を利用する行為は、既存の著作権法に違反する可能性が高いと主張。特に「Sora 2」のような生成AIが、特定の著作物を複製したり、それに類似する出力を生成したりする場合、機械学習プロセスにおける複製行為が著作権侵害に該当し得るとの見解を示している。これは、AI開発者に対し、著作権保護へのより厳格な対応を求めるものだ。
スタジオジブリも懸念:生成AIによる作品への影響
アニメーションスタジオのスタジオジブリも、OpenAIの生成AI製品による影響を強く受けている企業のひとつだ。TechCrunchの報道によると、今年3月にChatGPTの画像生成機能がリリースされて以降、「千と千尋の神隠し」や「となりのトトロ」といったジブリ作品のスタイルで、ユーザーが自身の写真やペットの画像を再現することが人気のトレンドとなった。
この現象は、AIが特定の画風やキャラクターを模倣する能力を浮き彫りにした。OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏自身も、X(旧Twitter)のプロフィール画像を「ジブリ風」に加工した画像に変更したことを投稿している。この状況は、著作権者にとって作品の模倣に対する懸念を深めるものとなった。
スタジオジブリの中心的人物である宮崎駿監督は、AIによる作品の模倣について直接コメントしていない。しかし、2016年にAIが生成した3Dアニメーションを見た際には「生命そのものへの侮辱」と述べ、「見るに堪えない」と強く嫌悪感を示した。これは、AI技術が人間の創造性に及ぼす影響に対する彼の根本的な姿勢を示唆している。
OpenAIのスタンスと米国著作権法の現状
OpenAIの著作権コンテンツへのアプローチは「許可ではなく許しを請う(ask forgiveness, not permission)」ものだと報じられている。この姿勢は、ユーザーが著作権で保護されたキャラクターや故人のディープフェイク画像を容易に生成できる状況を生み出している。これにより、任天堂やマーティン・ルーサー・キング・ジュニア財団といった団体からも苦情が寄せられている。
米国では、AI学習における著作物利用に関する著作権法の解釈が不明瞭なままだ。1976年以来、著作権法自体が大幅に改正されておらず、AIのような新しい技術の出現に対応しきれていない。これにより、判事たちは著作権法の解釈において明確な判例に乏しい状況にあると、米国著作権局の資料も指摘している。
しかし、直近の判決では、米国の連邦判事がAnthropic社が著作権で保護された書籍をAI学習に利用したこと自体は違法ではないと判断した事例がある。ただし、同社は学習に用いた書籍を不正に入手したとして罰金を科されている。この判決は、AI学習における著作権侵害の判断の難しさを示している。
日本独自の著作権観点と法的措置の可能性
CODAは、米国とは異なる日本の著作権制度において、OpenAIの行為が著作権侵害に該当する可能性があると主張している。日本の著作権制度では、著作物の利用には原則として事前の許諾が必要とされる。また、「事後的な異議申し立てによって侵害の責任を免れる制度はない」とCODAは強調する公式見解で述べている。
これは、たとえ著作物がAI学習に利用されても、それが「公正利用」として認められやすい米国法とは対照的だ。日本においては、機械学習プロセスで著作物が複製される行為そのものが著作権侵害を構成し得ると考えられている。特に「Sora 2」のように特定の著作物を再現したり、それに類似するコンテンツを生成したりする場合、より深刻な侵害とみなされる可能性が高い。
このため、OpenAIがCODAの要求に応じない場合、 aggrieved parties(権利侵害を受けた当事者)は法的措置に踏み切る可能性がある。日本の著作権法に基づく訴訟は、AI学習における著作物利用の新しい法的基準を確立する動きとなるかもしれない。これは、AI開発と著作権保護の未来に大きな影響を与えるだろう。
参考リンク
- CODAがOpenAIに書簡を送付したという発表
- Automaton Mediaによる日本のパブリッシャーの要求に関する報道
- TechCrunchによるスタジオジブリとAIコピーに関する記事
- サム・アルトマン氏のXアカウント
- サム・アルトマン氏の「Ghiblified」X投稿
- TechCrunchによるマーティン・ルーサー・キング・ジュニア財団の苦情に関する記事
- 米国著作権法(Title 17)の原文
- TechCrunchによるAnthropicの著作権訴訟に関する記事
- 宮崎駿監督のAIに関する発言(YouTube)
- 米国著作権局によるAIと著作権に関する報告書
- GameSpotによるスタジオジブリと日本のゲームパブリッシャーの要求に関する記事